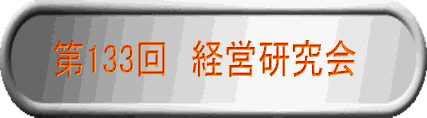
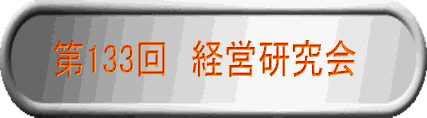
| 《日 時》 | 平成24年1月19日(木) |
| 《講 師》 | 中国古典研究家・作家 守屋 淳 氏 |
| 《テーマ》 |
〜中国古典の知恵を現在にどう活かすか〜 |
| 1.「戦争論」による戦いの本質 「孫子」の兵法は、現代の処世術やビジネス戦略にも関係し、私たちにも役に立つものとなっています。「孫子」は孫武が2500年前に記したものですが、ジャンルや時代を超えて非常に活用されている兵法書です。 「孫子」と真逆の兵法書に「戦争論」(クラウゼヴィッツ著)があります。西洋における戦略書のバイブルです。「戦争とは、決闘を拡大したもの」であり、戦いの本質とは、 1.一対一で戦う 2.やるかやられるか と定義しています。これではお互いの手の打ち合いが分かり、エスカレートしていきます。ビジネスの例でいうと、値引き合戦です。最終的には、地力に勝る方が勝ちます。つまり、経営資源が大きい方が勝つ、ビジネスでいう「同質化戦略」です。業界で一位の企業は、二位以下の企業のやる良きことを全て真似すれば、一位としての地位を維持できます。 地力が同程度ならば、指揮官がより天才的な方が勝ちます。ひらめきは1〜2割のもので、より少なく相手より間違った手を打つことで勝敗は決まります。戦う人間の能力の差で決まるのです。 |
| 2.「孫子」の前提条件 1.ライバルは多数存在 体力や経営資源をすり減らさず、自分以外の二社が泥沼の状況に陥ってくれる戦いこそ、漁夫の利をさらえる立場で望ましいのです。 2.やり直しが利かない 孫武が直面した時代は、550年間続く戦乱の世で、一発勝負の状況でした。 『戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり』(戦わないで敵を降伏させることこそが、最善の策なのである。) これは現代の政治的外交戦略です。相手が自分より弱い場合は、軍事力、国力をうまく利用して、戦わずに味方にさせることを実現させます。相手が同等の場合は、頭を使って戦います。エネルギーを向けてきたら、早期に芽を摘み、エネルギーを反らすことで第三者に目を向けさせます。また、相手が強ければ、いったんは強いものの味方、傘下になり、最終的に覇権を握るようにしていきます。なるべく戦わないようにする、戦略の有効な手です。戦国時代の徳川家康もその例です。 |
| 3.「孫子」による戦いの基本原則 戦うまいと思っていても、自分に守るものがある場合は、守るために戦わざるを得ません。 戦いの基本原則は、2つあります。 1.短期決戦 確実に勝てる場合は戦うが、確実に勝てない場合は戦わず、政治的外交戦略を駆使します。 2.不敗の活用 自分の努力次第で負けていない状況は達成できます。勝てるかどうかは敵次第ですので、敵や環境のチャンスを逃しません。 戦いにおける原理原則とは、以下のとおりです。 1.最初から勝利を目指す 2.不敗を守り続ける 3.不敗から勝利へ 戦いのノウハウは、崩し技と決め技の2つに分類できます。決め技で最終的に勝つのは、 1.兵員物量に勝る 2.精神力で勝る 3.情報に勝る ということです。 |
| 4.精神力で勝るとは 勢いは一人ひとりの実力を発揮させ、かさ上げさせます。だれしもやりたくないことをやらせ、かつ、やる気にさせ、勢いに乗せるには、生存本能を刺激すればよいのです。 人の士気、組織の勢いは盛衰するものです。やりたいことをやっている時の勢いは、勝ち味を覚えさせること、例えば、お客様や上司といった第三者からの評価を得ることが必要です。絶体絶命の窮地に追い込んだり、ほめてやったりすることで、勢いに乗せて勝っていってください。 現代ビジネスにも通ずる中国古典を豊富な引用で分かりやすく、ご紹介いただきました。 |
| K・T |
 ホーム |
|
 |